法人を設立したあと、まず行うべき大事な手続きが「税務関係の届出」です。
設立登記が完了しても、国や自治体がその法人を正式に“課税対象”として認識するためには、各所に届出を出す必要があります。
ここでは、届出先が 税務署・都道府県税事務所・市町村役場 と3か所に分かれる理由と、それぞれの役割をわかりやすく解説します。
1. 届出先が3か所ある理由
結論から言うと、支払う税金の行き先(管轄)が違うからです。
日本の税金は大きく「国税」と「地方税」に分かれ、それぞれを管理する行政機関が異なります。
| 区分 | 税金の種類 | 管轄 | 届出先 |
|---|---|---|---|
| 国税 | 法人税、源泉所得税、消費税など | 国(国税庁) | 税務署 |
| 地方税(都道府県税) | 法人事業税、法人都道府県民税 | 都道府県 | 都道府県税事務所 |
| 地方税(市町村税) | 法人市町村民税(法人税割・均等割) | 市区町村 | 市町村役場 |
つまり、
「誰に税金を納めるか」=「どこに届出を出すか」
という関係になっています。
2. 各届出の目的と内容
(1)税務署への届出(国税)
- 対象となる税金:法人税、源泉所得税、消費税
- 主な届出書類
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書(任意)
- 提出期限:設立から2か月以内(原則)
税務署は「国税」を管理するため、法人税や源泉徴収などの課税・納付を把握する目的で届出を求めています。
(2)都道府県税事務所への届出
- 対象となる税金:法人事業税、法人都道府県民税
- 主な届出書類:法人設立・設置届出書
- 提出期限:設立から1か月以内(都道府県により異なる)
都道府県が課す税金の対象として法人を登録するための届出です。
事業の種類や所在地などによって税率が変わることがあります。
(3)市町村役場への届出
- 対象となる税金:法人市町村民税
- 主な届出書類:法人設立届出書
- 提出期限:設立から1か月以内(自治体により異なる)
市町村が課す「法人市民税」の課税対象として登録するための届出です。
黒字・赤字に関係なく、**均等割(最低7万円程度)**が毎年かかるため、必ず提出が必要です。
3. 各税金のおおまかな負担割合
利益が出た場合、国税と地方税を合わせて おおよそ20〜30% 程度が税金としてかかります。
| 税区分 | 主な税金 | 税率の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国税 | 法人税 | 15%(800万円以下)、23.2%(超部分) | 中小企業は軽減あり |
| 都道府県税 | 法人事業税 | 約3.5〜7% | 所得に応じ段階的 |
| 市町村税 | 法人住民税(法人税割) | 約10%(法人税額に対して) | 自治体により差あり |
| 市町村税 | 法人住民税(均等割) | 7万円〜 | 赤字でも発生 |
4. 赤字でも支払う税金はある?
はい。
利益が出なくても、法人住民税の均等割だけは必ず発生します。
これは会社の規模(資本金・従業員数)に応じて定額で課されるもので、事業を行っている限り毎年納付が必要です。
5. まとめ
| 届出先 | 管轄する税金 | 届出の目的 |
|---|---|---|
| 税務署(国) | 法人税・源泉所得税・消費税 | 国が法人を課税対象として把握するため |
| 都道府県税事務所 | 法人事業税・法人県民税 | 都道府県が事業所課税を行うため |
| 市町村役場 | 法人市民税 | 均等割を含む住民税を課税するため |
✍️ 最後に
法人を設立したら、登記だけで終わりではなく、税務関係の届出がスタート地点です。
どこに何を出すかを整理しておくことで、後から「届出漏れ」や「納付漏れ」によるペナルティを防げます。
管轄の役所や期限は地域によって異なるため、所在地に応じた手続き方法も必ず確認しましょう。

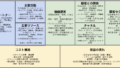
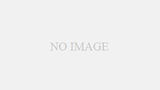
コメント